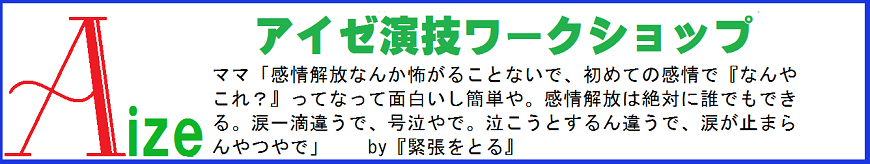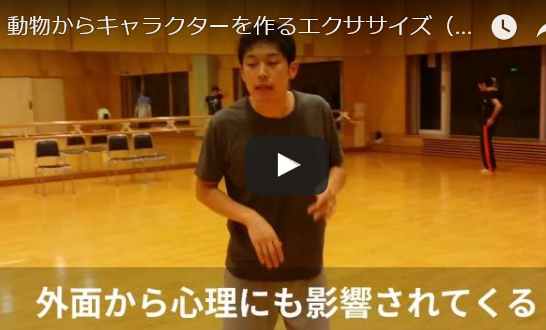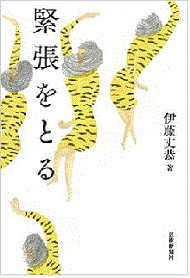役作りの方法
アイゼ代表
伊藤丈恭の本
『緊張をとる』
おかげさまで
amazon演劇書ランキングで
1位を獲得する事が出来ました
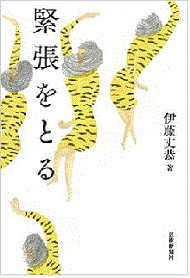
一般的には知られていない
緊張の原因と対処法を
社会人・俳優ともに効果のある
演劇的アプローチで解決します
|
【内容】
・成功しようとするのでなく、
失敗を回避すると成功する
・楽観的に構想し、
悲観的に計画し、
楽観的に実行する
・躊躇はすぐに取れる
・読み合わせを本気でしてはダメ
・イメージを持つ危険性
・ポジティブだと演技が伸びない
・諦めを上手に使えば演技は伸る
・役作りの方法
・脳のリラクゼーション など |
アイゼの演技
『ジョゼと虎と魚たち』
有名映画監督に「本当の感情。泣き声に切なさが表れている」 と称賛していただいた演技です。
あなたは演技で号泣できますか?
演技を始めて1年の人たちの
アイゼ・アプローチでの役作りです。

あえてトム・ハンクス『big』の子供役の演技と比較
アイゼ・アプローチで自由な子供のキャラクターを作り、それでオーディションに合格して仕事を得た人が多数います。
アイゼに入って2か月の人です。

印象に残るキャラクターを作る エクササイズ
演技でキャラクターゼーションを使えることは武器になります。
オーディションにも効果的です。
多くの人がキャラクターゼーションを習ったこともないのではないですか?
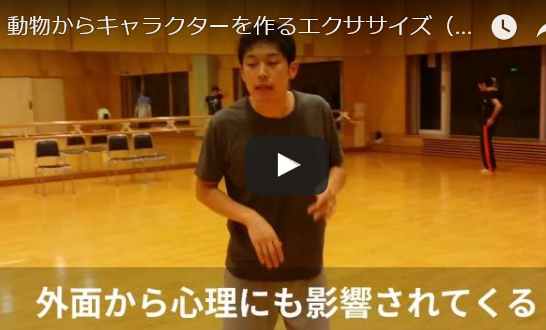
|
役作りの方法 (内面のみ 外面は除く)
まず最初に
- 客観的に何度も本を読む。ストーリー・事件の流れ、人間関係、状況をつかむ
- 次に主観的に読む。そのとき無理に感情をつかもうとしない。自然と心に感じたのならいいが、そうでないのなら頭の解釈だけの演技にならないために。
役の準備で焦りは禁物。
- その役の何が好き?どこが共感できる?
役の想い・苦しみ・喜びなどを代弁したいという気持ちはあるか?
そういう気持ちを見つけようとせず、だけど「上手にやる」とがんばっても、どうしても表面上の役でしかなく、 微妙な想い・叫びに気付いてあげれず、自分の深い感情を使うことが出来ない。
内面の準備
- ※本に書かれていない過去の部分をつくっておく。
- 本に書かれている事を、まるごと・そのまま信じ込もうなどとしない。
自分ごとにしていかないと、 想像力も働かないし、心も動かない。
役の体験と同じような体験を見つけ、役の心情を理解してあげる。
(少しぐらい違っていても、正当化出来るならばよい)
次に役の体験と自分の体験をリンクさせ、自分に役を馴染ませていく。
決して、その時の自分の感情を演技にはめ込もうとしない。
はめ込まれた感情は、無理強いされていて型にはまり微妙なフィーリングが表れず、 また作品全体を通すとつぎはぎだらけで一本スジが通らなくなるから。
大丈夫、深く心情を理解してあげれてたら、自然な感情が自然とあふれてくるから。
- その役と自分の価値観の似ているところ、似ていないところをはっきりとさせなぜ違うのか自問する。
・「もし、この状況で私が役の人物なら私は何をするだろう?」
(スタニスラフスキー)
・「私は役がこの状況でやっている事をする為に何を準備すべきか?」 (スタニスラフスキーの一番弟子のワフタンゴフ)
・「もし、自分の人生のあれがこうだったら役と同じ事をするだろう」
というように、 作品を歪めない程度に正当化して自分の中に役の要素を見つける。
例)自分はわりと勉強が出来る方だったが、もし、勉強できない方だったら役と同じように劣等感を感じ、 目立たないように気をつけるかもしれない。
自分は運動が苦手で体育の時間に劣等感を感じていたのと同じような気持ちなのかもしれない。
- 超課題(目的)を見つけはっきりさせる。
超課題とは役を突き動かす物。課題がはっきりすると、 行動・セリフの方向性がはっきりし、結果心理的なものを自然に流れるように導く。
何をしたいのか? 何になりたいのか? なぜしてるのか、など。
作品を通しての大きな課題、
ある期間限定の課題、
そのシーンにおける課題
- 反対の面を見つけ役の内面へアプローチする。
例えば、ものすごく積極的に仕事をする役があったとする。
俳優はその役が「仕事が好き」「お金が欲しい」「昇進したい」という方向からアプローチしがちだが、 その役は臆病で少しでも怠けてクビになるのが怖いだけなのかもしれない。
あるいは、お金が好きでケチに見える人は、実はたくさん寄付する為にケチになったのかもしれない。
- 役になりきろうとしない。
それをすると、意識・注意の方向が内側にこもり、何も感じず、 当然役になりきる事も出来ない。
なりきろうとするのでなく、的確な超課題を見つけ、遂行しようとすればよい。
演技とは、なりきるというような一面性ではなく、役として感じ、それを操作しているという二面性が必要。
- 役の生活を想像し、想いをめぐらす。そのために、事実・事件・状況をはっきりさしておく。
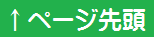
エクササイズ
- そのシーンである感情が必要なら、その感情を開くようなエクササイズを見つけ実行し、 シーンの時にその感情が出やすいようにしておく。
- 状況・相手役に対しての、役と同じ価値観を自分の中に見つけ育てる。
- 役と同じような体験を自分の過去からみつけ、共感共鳴・役の気持ちを理解し、その結果として 感覚・感情がよみがえりやすいようにエクササイズしておく。
- 舞台のセットでは俳優の心に影響を与えないから、、本番で想像の場所が出来るようにしておく。 想像の場所の雰囲気ができると、心が影響されやすいから。
- 可能な限り、役と同じ仕事などの環境を調べ、体験する。
セリフについて
- 上手にセリフを言おうとしない。そうではなく、役の内面を深く根気強く作るようにする。 内面が出来ればセリフの言い方も変わるから。
- リアリティーが出来ても、言い慣れていない言葉使いはやはり使いにくいもの。 だから、その言葉使いを何度もやり慣れておく。
- 特に語尾が死んでしまうことが多い。語尾を下げる、上げる、強める、弱めるだけでセリフの 意味が全然変わるので注意する。
- 自分のは当然、相手のセリフも完璧に覚え、そして捨てる(忘れる)。
ただでさえ、演技の時いろいろなものに集中しないといけないのに、セリフを思い出すことに たずさわっていると演技へのジャマになるから。
そして、覚えたセリフにしがみついてると、 その場で反応する事ができなくなるから。
大丈夫、完璧に覚えているならセリフに意識を持っていかなくても、瞬間瞬間に自然と出るから。
失敗してもいいから、セリフを手放してみる勇気を持つ事。
- セリフを事務的に感情を込めずに覚える。感情を込めて覚えると、解釈が違っていた時に 戻せなくなるのと、ワンパターンのセリフの言い方に固まってしまい、演技の時そのつど
感じて本当の微妙な表現の妨げになるから。
- セリフ・行動には動機・理由づけされてないといけない。
- 相手役のセリフをちゃんと聞く。自分から発しようとするのでなく、相手役から受け取ること を心掛ける。
- 最終的にはセリフ通りするのが理想だが、俳優訓練の初期の段階及び、その役にアプローチする。
初期の段階では、セリフを自分の言葉に代えてやっても構わない。
無理の無いところから入っていき、フィーリングをつかむ事が大事。
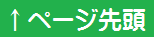
リハーサル
- リハーサルはその場で完成させる為にするのでなく、自分に足りない役の要素を見つける為にする。
まだ、完成させる時期でもないのに、急いで完成させようとすると気付かない内に小手先の演技に走ってしまう。
- 最初は棒読みで読み合わせをする。感情も入れず、解釈も決め付けないでやる。
何度か棒読みでやっているうちに何かを感じたり、「たぶんこういう意味だろう」というのがあったら、 ほんの少しだけ(20、30%ぐらい)感情を入れて読んでみる。
いきなり本気でやるのでなく、自分のフィーリングが自然に流れるか探りながらやる。
- 「注意の方向」「超課題」を見つける事が役を掘り下げる事で、リハーサルはそれを見つけるためにある。
だから、急いで完成させようとするのでなく、 ゆっくり棒読みで、確認しながらやる。
- 気持ちばかりを優先してやらないようにする。
行動がともなっていないと気持ちも自然と表れない。
例えば、相手役との距離はどうか?
すぐ隣と、 少し離れているのでは意味や気分が違ってくる時がある。
相手役の顔を見てセリフを言うのか、 反対を見ていうのかでも意味・気分が違ってくる。
- あまり感じようとしない。感じようとすると感じないものだから。
感じる事より相手役・セリフの意味・超課題に集中する。
それが上手くいくと気づかないうちに感じているものです。
- セリフで感情を表現しようとしない。ちゃんと役の準備ができていれば、自然とセリフの言い方も変わって、 表現しようとしなくても表れてくるから。
- リハーサルの段階では、アドリブを使ってもいい。
衝動を生かすためと、決まり事に縛られない自由な感覚を保つため。
- 上手くいった時の演技を繰り返そうとしない。繰り返すのは、リラックス・集中・心をかきたてる想像など。
衝動・感情を直接繰り返そうとして出来るものではないから。
- 本には書いてない役の生活をインプロビゼーション(即興)でやってみる。 これは自由な想像力をつかむのにすごく有効的。
|
|
|